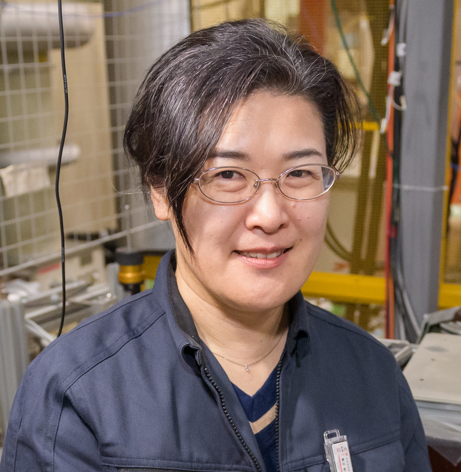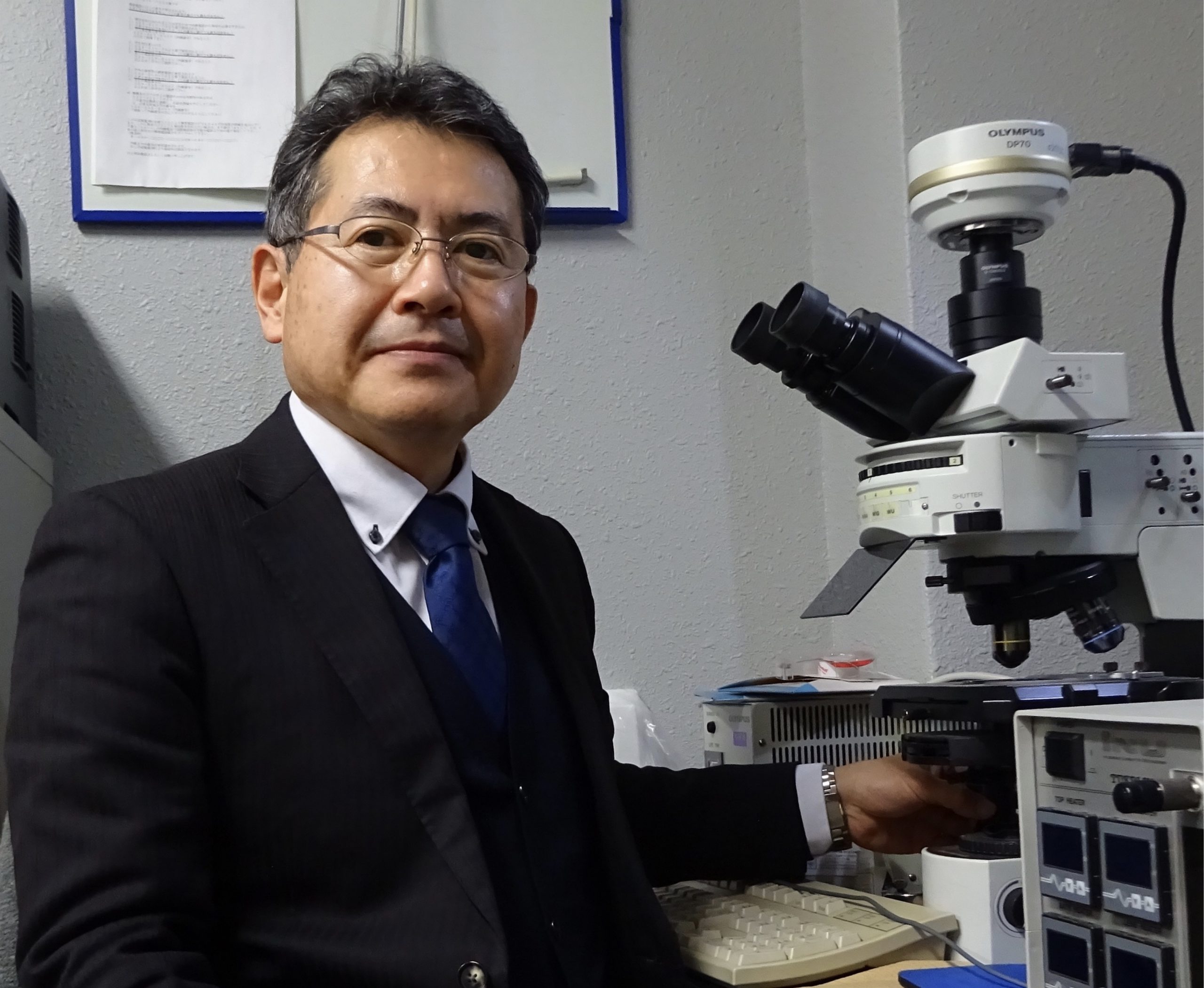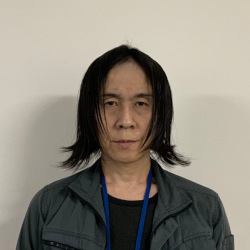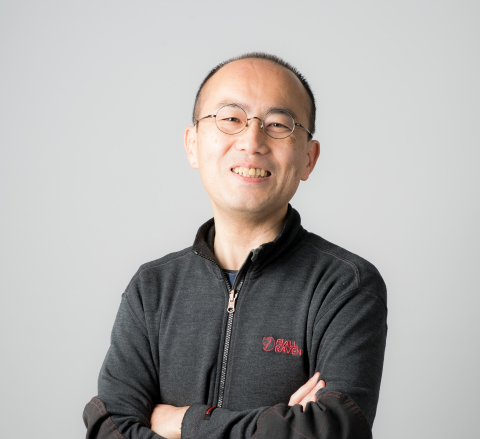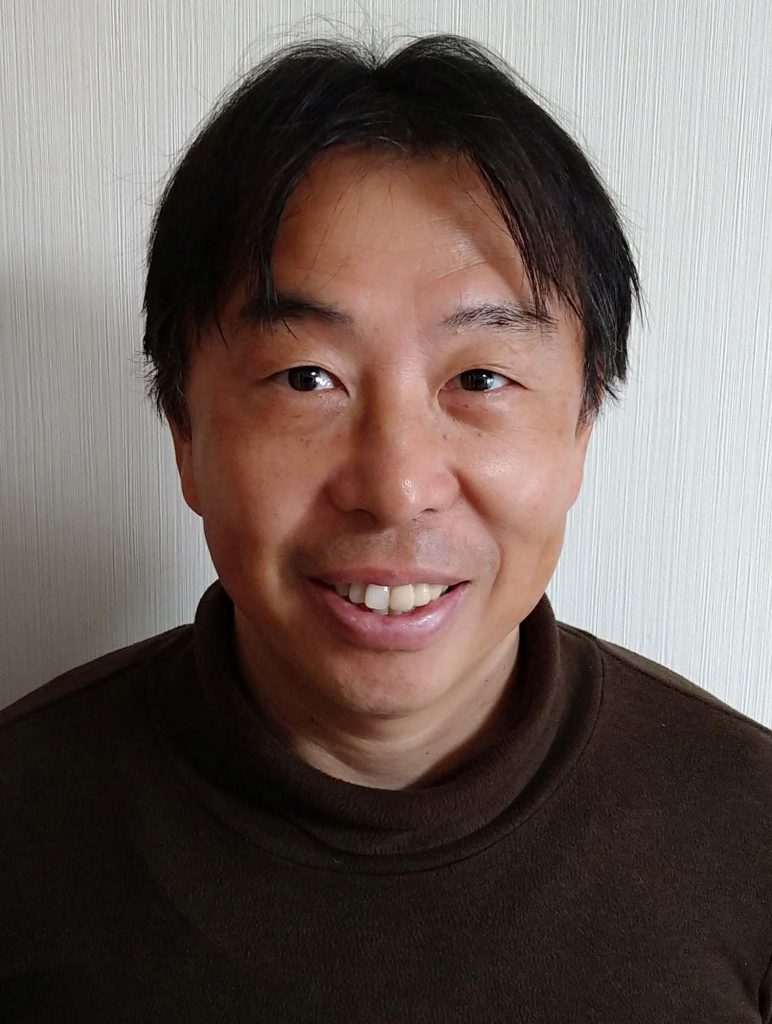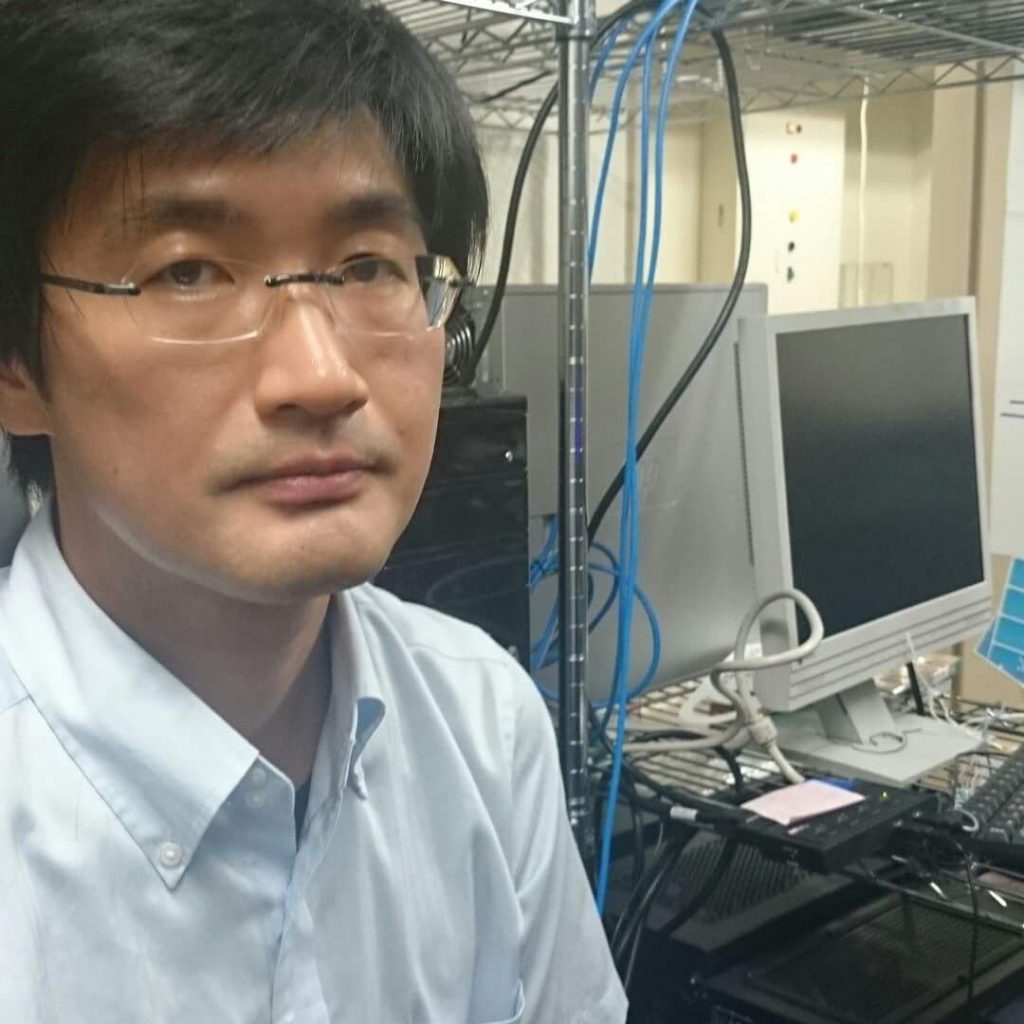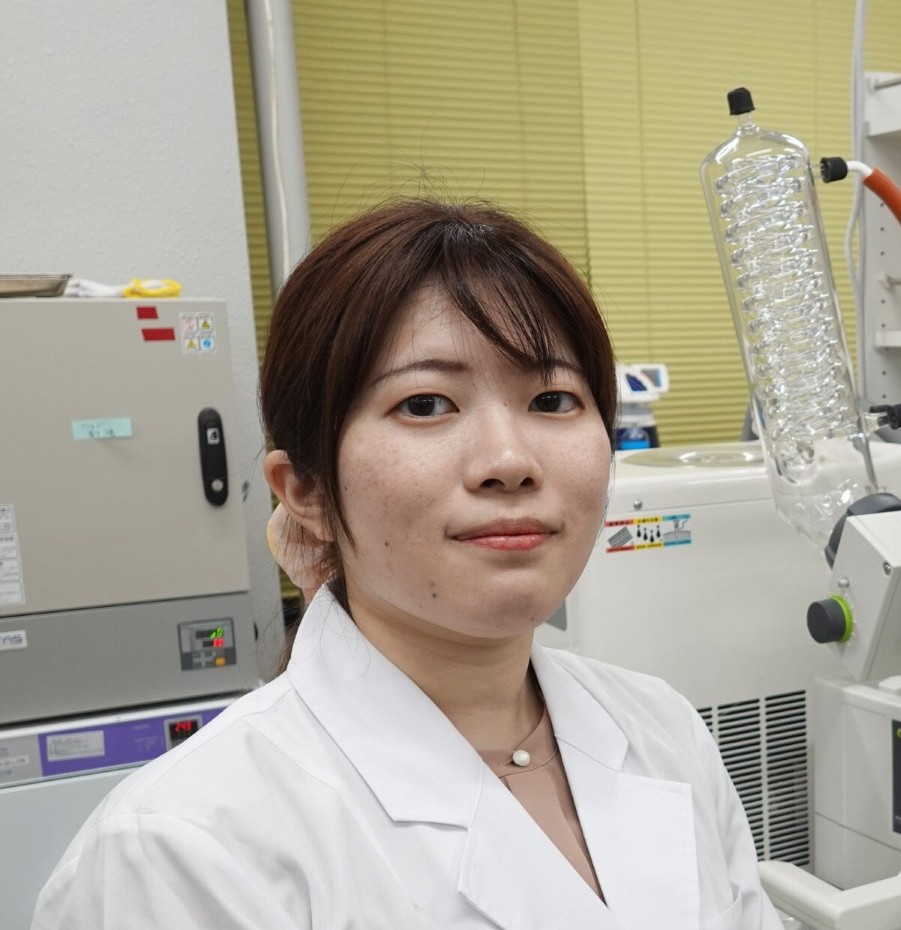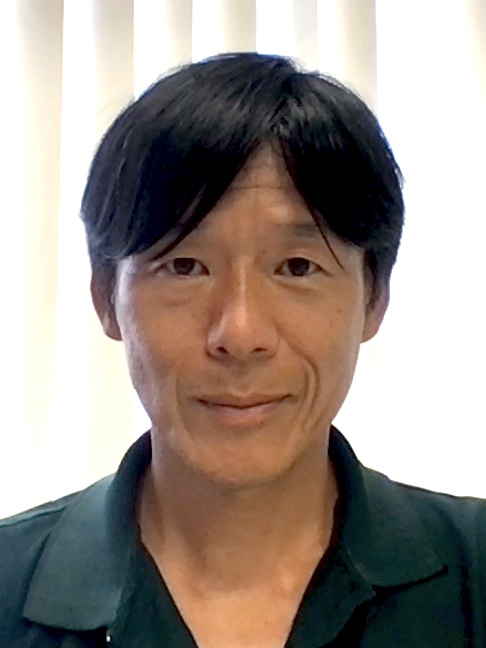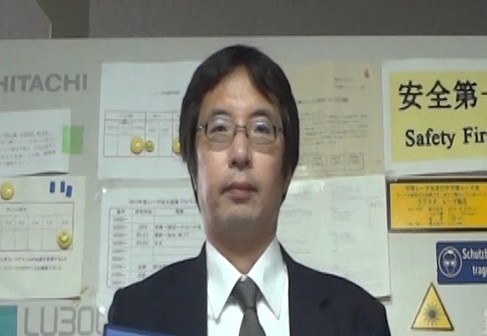原子科学研究教育センター 体制(2024年度4月1日発足、2025年5月1日現在)
メンバー紹介
| 社会/地域課題共考解決室 | 応用原子科学部門 | 次世代革新炉部門 | 放射線安全部門 | |
| センター研究プランの立案・共同研究マネジメント | 量子線科学・材料科学・基礎科学 | 安全な次世代原子炉・エネルギー源・社会とのコミュニケーション | 安全安心放射線科学・生命科学 | |
| 室長または部門長 | 室長:酒井 宗寿 | 部門長:星川 晃範 | 部門長:田中 伸厚 | 部門長:鳥養 祐二 |
| 専任教員 専務教員 URA | 酒井 宗寿、岩佐 和晃、 久語 輝彦、石塚 悦男、 原田 秀郎 | 岩佐 和晃、星川 晃範、 前田 知貴、大山 研司、 佐藤 成男、西野 創一郎、 飯沼 裕美 | 石塚 悦男、久語 輝彦、 田中 伸厚、松村 邦仁、 西 剛史、森 聖治、 矢木啓介 | 田内 広、中村 麻子、 鳥養 祐二、庄村 康人 |
| 兼務教員 | 桑原 慶太郎、池田 輝之、 横山 淳、中野 岳仁 | 山崎 和彦、森 孝太郎、 岩瀬 謙二、永野 隆敏 | 海野 昌喜、山口 峻英、 小畑 結衣 | |
| 連携分野 | エネルギー材料 次世代炉耐久材料 | 高温ガス炉 高速炉 核融合 高温化学反応 | 医療・創薬分野 | |
| 部門活動の方向性 | 次世代革新炉による発電や水素発生技術などを見据え、エネルギー問題に関する社会のニーズを分析し、分野融合、組織横断、施設連携型のプロジェクトを企画・立案。 | 茨城大学が独自に推進している量子線科学(中性子・放射光・ミュオン)を主眼とし、量子線先端計測技術の高度化、量子線利用による機能材料創生、量子線による基礎科学を推進。 | 次世代革新炉などによる安全な原子力の技術革新と利用を対象として、社会実装に向けた関連技術の開発・高度化、および原子力技術の継承。 | 生命・生体物質への影響を主な対象とし、放射線の安全利用技術・放射線の測定評価技術・放射線による生命活動の解明技術の向上。 |
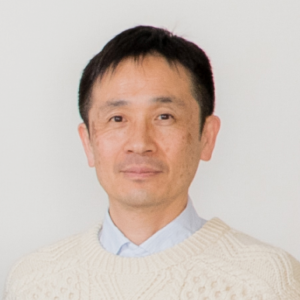
岩佐 和晃 教授
Kazuaki Iwasa
|研究活動等|
物質中に存在する多数の原子と電子は、磁性や超伝導などの特徴ある物性を示し、新たな現象と相状態の発見は未来の材料機能への道を開く可能性を秘めています。私は、単極子である電荷(正 or 負)や双極子である磁化(N極とS極のペア)といったよく知られた状態よりも高次の電子多極子や、カイラルのような非対称結晶構造ならではの磁性・半金属・超伝導など、新しい電子状態の自発的形成現象を対象として、その空間構造やダイナミクスをJ-PARCやJRR-3...
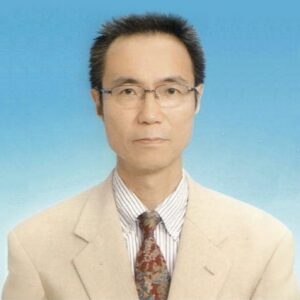
大山 研司 教授
Kenji Ohoyama
|研究活動等|
半導体などの材料では、その性能を異元素添加(ドープ)により制御しています。たとえば代表的なシリコン半導体では、わずか0.000001%のリンやホウ素をドープすることで実用になる性能を実現しています。大山研究室では、微少量ドープが母物質の格子に与える影響を直接可視化する手法である「白色中性子ホログラフィー」を世界で初めてJ-PARCで実現しました。ホログラフィー実験により世界で茨城大でしかできない特色ある機能性材料の研究を進めています。

星川 晃範 准教授
Akinori Hoshikawa
|研究活動等|
量子ビーム(主にX線や中性子)を利用することで得られるミクロな構造情報から、その材料特性との関連について研究しています。メタンハイドレートを代表するクラスレートハイドレートの構造特性をはじめ、酸化物であるセラミックスやプラスチックなど、様々な材料に関するそのミクロな構造をテーマとして取り扱っています。一方でこれらの計測や解析に必要な自動制御に関するシステム開発も行っています。

田中 伸厚 教授
Nobuatsu Tanaka
|研究活動等|
オリジナル・コードの混相流(固体・液体。気体)解析コード「CRIMSON」および超並列処理による流体粒子法コード「PARTITA」を開発。「CRIMSON」を用いて、GTIE GAPファンド2024プロジェクトの「原子力発電所廃炉プロセスの高度化及び除染・炉心解体技術の改良に資するデジタルツイン技術の概念検証」に取り組む。本プロジェクトで導入した高出力レーザーを用いて、実験と解析の両面からのレーザー溶断技術の研究開発を行う。...

西 剛史 教授
Tsuyoshi Nishi
|研究活動等|
原子力発電所や高速炉のシビアアクシデント解析において、炉心部で溶融した制御棒材(炭化ホウ素)と原子炉構造材(ステンレス鋼)との溶融混合物の特性を把握することは必要不可欠です。特に粘度の物性値は最も重要な物性値とされています。このような溶融混合物の粘度を系統的に取得するため、るつぼ回転粘度計を用いた高精度な粘度測定を実施しています。その他、高レベル放射性廃棄物処理用の固化ガラスの有力な...
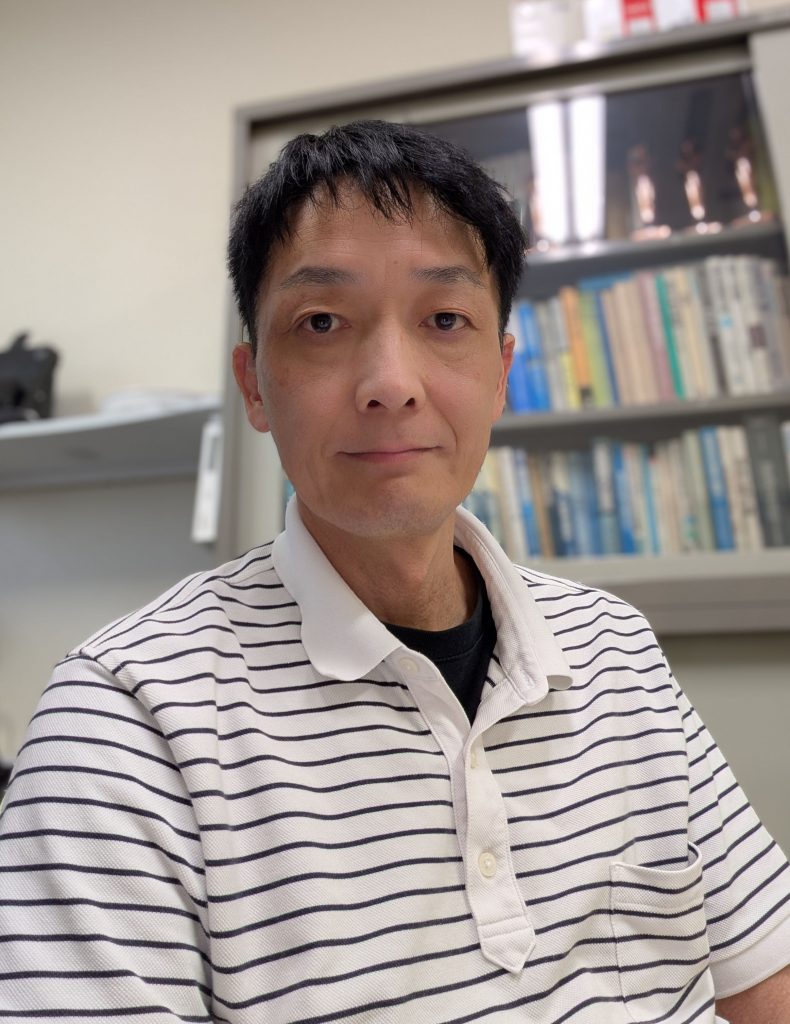
佐藤 成男 教授
Shigeo Sato
|研究活動等|
自動車、電機、精密機械といった川下産業の競争力を根幹から支え、わが国の国際的プレゼンスを左右するのが金属材料です。強度、延性、磁性、導電性といった多彩な機能特性のさらなる向上が求められる中、それらの起源であるミクロ組織に着目した革新的材料開発が不可欠となっています。こうした背景のもと、私たちは中性子、X線、電子線といった先端プローブを駆使し、ミクロ組織の精緻な解析技術の開発に取り組んでいます。

森 聖治 教授
Seiji Mori
|研究活動等|
私たちの物理有機化学研究室では、理論および計算化学的手法を駆使し、以下の二つの柱を中心に研究を展開しています。
- 生体内有機化合物および酵素の機能解明に向けた基礎研究
- 高選択的触媒化学反応の反応機構解析と、それに基づく新規反応・材料・触媒の設計
...

中野 岳仁 准教授
Takehito Nakano
|研究活動等|
多孔質結晶が有する配列ナノ空間を利用した新しい相関電子系の創生や、炭素の新奇ネットワーク物質の開発、酸素分子に由来する磁性の研究などを行っています。これらの新物質に対して、分光、磁性、電子スピン共鳴の実験や、ミュオン、中性子、放射光などの量子ビームを活用した実験を行うことで、多体電子系の物理の謎に迫るとともに新しい現象の発見を目指しています。

松村 邦仁 准教授
Kunihito Matsumura
|研究活動等|
原子力分野において、「熱流動」と呼ばれる研究をしています。気体と液体が混在する流れ(気液二相流)を中心に、原子炉の徐熱に関わる研究や過酷事故時に想定される熱や流体が関わる複雑な事象の研究を行っています。カーボンニュートラル社会への移行も踏まえて、気体と液体の流れ場の制御にも関心を持って研究を進めています。